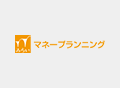大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。
「教育資金って、気づいたら足りない…」
「今さら学資保険?それともNISA?」
そんな声をよく耳にします。
大学進学など将来の大きな支出に備えるには、
「早く・計画的に・ムリなく」がカギ。
今回は、教育費のためにどのくらいの金額を、どのように準備していけばいいのかを、わかりやすく解説していきます。
■ 教育費は「三段階」で必要になる
教育費は「高校卒業=一括でかかる」と思われがちですが、
実際には以下のように段階的に増えていきます。
幼児~小学生:比較的少なめ(習い事や学童など)
中学生~高校生:じわじわ増加(塾・模試・受験費用)
大学:一気に大きな支出(入学金・授業料・下宿費など)
つまり、「大学資金だけを意識する」のではなく、
中学~高校のタイミングでもお金が必要になることを踏まえて準備する必要があります。
■ 目安はいくら?「大学進学に向けた貯蓄の目安」
ざっくりとした貯蓄の目安は次の通りです。
| 通学区分 | 必要資金の目安 | 月々の積立目安(18年間) |
|---|---|---|
| 自宅通学(国公立) | 約350万円 | 約1.6万円 |
| 自宅通学(私立) | 約500万円 | 約2.3万円 |
| 下宿あり(私立) | 約900万円 | 約4.2万円 |
※出産後すぐに積み立てを開始した場合。
途中から始める場合は、毎月の積立額が増えるため、**「早く始めるほど有利」**なのがわかります。
■ 貯め方の選択肢は3つ
教育資金を準備する手段には、大きく分けて次の3つがあります。
① 学資保険:昔ながらの「確実型」
決まった保険料を支払えば、18歳で満期金が受け取れる
元本保証で、返戻率が高い商品を選べばリスクが少ない
保護者が亡くなった場合でも保険料の支払い免除
安心感が大きい反面、途中解約のリスクや利回りの低さもあるため、目的を明確にして選びましょう。
② つみたてNISA:今注目の「成長型」
月1万円から始められ、運用益が非課税
投資信託で運用するため、リスクはあるがリターンも期待できる
教育費以外にも柔軟に使えるメリットあり
長期間コツコツ積み立てることで、複利効果を活かせるのが魅力。
ただし、元本割れの可能性もあるため、リスク許容度に応じた銘柄選びが大切です。
③ 銀行預金・定期積立:いつでも使える「柔軟型」
使い道に縛りがなく、途中で引き出しも自由
リスクがない代わりに、利息はごくわずか
「万一のときの備え」や「すぐ使うお金」を確保する意味で、現金ベースの積立も併用するとバランスが良くなります。
■ 3つの方法、どう組み合わせる?
おすすめは、「目的」と「期間」に応じて組み合わせること。
| 目的 | 商品 | 割合の目安 |
|---|---|---|
| 安定・保障重視 | 学資保険 | 40% |
| 資産成長を狙う | つみたてNISA | 40% |
| すぐ使える安心資金 | 銀行預金 | 20% |
家庭の収入状況や教育方針によって配分は変わってきますが、「一つに偏らないこと」がポイントです。
■ 教育資金づくり、今日からできること
教育費の準備は、「できる時に・できるだけ・こまめに」が基本。
今日から始められる小さな一歩は、こんなことです。
家計簿を見て、毎月1万円を教育費に回せるかチェック
銀行口座を「教育費専用」にして、積立スタート
つみたてNISA口座の開設を検討
保険証券を見直して、学資保険の見積りを取ってみる
「やらなきゃ…」と思っているだけでは、お金は貯まりません。
少額でも“始める”ことが、数年後に大きな安心感につながります。
みらいマネープランニングでは、家計の見直し、ライフプラン設計、住宅購入相談、将来の年金相談、NISAやiDECOなど、随時初回無料で相談(1時間)をお受けしています。メールでお問い合わせください。
お金の小学校大分校では、7月、8月も授業開催予定しています。
まずは、お金に関する基礎知識を学びたい方はお気軽にご参加ください。
授業日程が合わない方は個別にて開催しますので、一度ご相談ください。