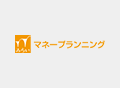大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。
今日は、医療費の自己負担を抑える「高額療養費制度」の改正と、
家計への影響、そして今からできる備えについてお話しします。
高額療養費制度とは?
高額療養費制度は、病気やけがで医療費が高額になったとき、
1か月の自己負担額に上限を設けて超えた分を払い戻す制度です。
たとえば、入院や手術で医療費が30万円かかったとしても、
所得に応じた上限を超えた分は後から戻ってきます。
この仕組みのおかげで、重い病気でも経済的な不安を少し和らげ、
安心して治療に向き合うことができる人が増えています。
改正が予定されていた内容
政府は当初、2025年8月から自己負担上限を引き上げる方針を示していました。
たとえば、年収500万円台の世帯では、
月あたりの上限が約7,800円増えるという試算が出ていました。
さらに高所得層では、月4万円以上の負担増となる可能性も指摘されていました。
こうした案に対し、患者団体や医療関係者から
「負担が重すぎる」「治療をためらう人が出るのでは」
といった強い反発の声が上がりました。
その結果、2025年春に一時見送りが決定。
現時点では改正は行われていませんが、
政府は2025年秋までに再検討する方針を示しています。
つまり、「いったん止まったけれど、今後また見直される可能性がある」という状況です。
もし改正されたらどうなる?
仮に上限が引き上げられた場合、
入院や手術などで医療費がかかる人ほど、月々の自己負担が増えることになります。
また、年収が高い人ほど影響が大きくなる傾向があります。
さらに、現在は同じ病気で長期間治療が続いた場合に負担が軽くなる
「多数回該当(たすうかいがいとう)」という仕組みもありますが、
この制度も見直しの対象とされていました。
一方で、もともと制度の対象外となっている費用にも注意が必要です。
差額ベッド代
先進医療の技術料
通院交通費
これらは高額療養費制度ではカバーされないため、
今後も自己負担が前提となります。
今からできる3つの備え
制度が変わるかもしれない今、
私たちができる備えを3つご紹介します。
① 限度額適用認定証を取得しておく
事前に申請しておくことで、入院や手術の際に窓口での支払いが上限内に抑えられます。
退院後に払い戻しを待つ必要がないため、
手元資金の減りを最小限にできます。
② 医療保険・就業不能保険を見直す
高額療養費制度ではカバーされない費用(差額ベッド代・先進医療など)に備えるには、
民間の医療保険やがん保険が有効です。
また、長期の入院や治療によって収入が減る場合に備えて、
「就業不能保険」も検討の余地があります。
③ 生活防衛資金を確保する
制度を利用しても、一時的には医療費を立て替える必要があります。
貯蓄が少ないと、払い戻しまでの間の生活費に困ることも。
生活費の3〜6か月分を緊急用の資金として確保しておくと安心です。
まとめ
高額療養費制度は、医療費の負担を軽くしてくれる大切な仕組みです。
2025年の上限引き上げは一時見送りとなりましたが、
今後再び議論される可能性があります。
制度が変わるとき、いちばん影響を受けやすいのは「知らなかった人」です。
限度額認定証を取得する
保険を見直す
緊急資金を準備する
この3つを意識しておくことで、万が一の医療費にも慌てずに対応できます。
「うちの家計や保険は大丈夫かな?」と感じた方は、
早めに専門家へ相談してみましょう。
みらいマネープランニングでは、家計の見直し、ライフプラン設計、住宅購入相談、将来の年金相談、NISAやiDECOなど、随時初回無料で相談(1時間)をお受けしています。メールでお問い合わせください。
お金の小学校大分校では、10月、11月も授業開催予定しています。
まずは、お金に関する基礎知識を学びたい方はお気軽にご参加ください。
授業日程が合わない方は個別にて開催しますので、一度ご相談ください。